
きょうは近くの、北海道立帯広美術館へ。
北大路魯山人(1883-1959)の食器を観に行きました。
魯山人の「器」は、実際に食卓に置かれる「用」の美として、
その格調の高さに圧倒されます。
青磁/赤絵/九谷/織部/信楽/瀬戸/志野/備前/唐津・・・・。
そして漆器・書画・濡額の刻字・・・。
わが国伝統工芸の、懐深い技の世界に、遊ぶように更新される、
旺盛な制作遍歴を一堂に集めたそれは、
ひたすら、「食」の空間を引き立たせる、
あくなき審美への探求でもあるのです。
美と食の殉教者といいますか、ひとつひとつの器や書を廻る鑑賞も、
こういうこともしました。こういうことも出来ます。
と、まったく臨機応変な自慢話のようでいて、
観ていて、じつに楽しいのは、
それがあくまでも、「美意識」に貫かれているからなのです。
「食」を通しての「美」の洗練。
ほんと、憧れますね、「美食倶楽部」。
しかし、美しいものには、かならず物語があります。
留まるところを知らない山人先生の生き方は、
また、多くの伝説をも生みました。
やはりこういう「巨人」には、傍に居る俗人は厄介でもあるのでしょう。
・・・いまでは、マンガにもなっているので、
例のパリの「トゥール・ダルジャン」のエピソード(すき焼きと鴨料理)とか、
短絡して勘違いする半可通も多いので、
ここはエッセイから、基本的な一節を以下引用します。
・・・まことに、「伝統」とか「洗練」とかは、
じつに有り難いものなのであります。

―――『魯山人の料理王国』(文化出版局1980)より。
納豆の茶漬 (174P) ■納豆のこしらえ方
・・・・・・・・・・・・
ここでいう納豆のこしらえ方とは練り方のことである。
この練り方がまずいと、納豆の味が出ない。
納豆を器に出して、
それに何も加えないでそのまま二本の箸でよく練りまぜる。
そうすると、納豆の糸が多くなる。
蓮から出る糸のようなものがふえて来て、
かたくて練りにくくなって来る。
この糸を出せば出すほど納豆はうまくなるのであるから不精をしないで、
また手間を惜しまず、極力練りかえすべきである。
かたく練り上げたら醤油を数滴落としてまた練るのである。
また醤油数滴を落として練る。
要するにほんの少しずつの醤油をかけては練ることを繰り返し、
糸のすがたがなくなってどろどろになった納豆に、
辛子を入れてよく攪拌する。
この時、好みによって薬味(葱の微塵切り)を少量混和すると、
一段と味が強くなってうまい。
茶漬であっても無くても、納豆はこうして食べるべきものである。
最初から醤油を入れて練るようなやり方は下手なやり方である。
・・・・・・・・・・・・・
■だしの取り方 (205P)
・・・・・・・・・・・・・・
昆布のだしを取るには、
まず昆布を水でぬらしただけで一、二分ほど間をおき、
表面がほとびた感じが出た時、
水道の水でジャーッとやらずに、
トロトロと出るくらいに昆布を受けながら、
指先で器用にいたわって、
だましだまし表面の砂やごみをおとし、
その昆布を熱湯の中ヘサッと通す。
それでいいのだ。
これではだしが出たかどうか、心配なさるかも知れない。
出たか出ないかはちょっと汁を吸ってみれば、
無色透明でも、
うま味が出ているのがわかる。
量はどのくらい入れるかは実習すれば、すぐに分かる。
このだしは鯛のうしおなどの時は是非なくてはならない。
昆布を湯にさっと通したきりで上げてしまうのは、
なにか惜しいように考え、
長くいつまでも煮るのは愚の骨頂、
昆布の底の甘味が出て、
決して気の利いただしはできない。
京都辺では引出し昆布といって、
鍋の一方から長い昆布を入れ、
底をくぐらして一方から引き上げるというやり方もあるが、
こういうきびしいやり方だと、
どんなやかましい食通たちでも、
文句の言いようがないということになっている。
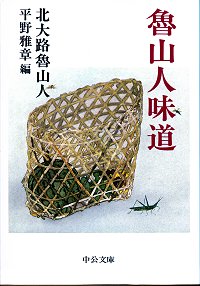
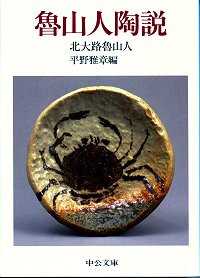
#■BOOK
