これまでに掲載した全米禁酒法についての記事を読み返してみたのですが、時間軸が前後してとても分かりにくいのに気づきました。そこでちょっと整理して、前回と今回の2回にまとめ直してみました。一部、文章と図表も追加しています。
禁酒運動でもっとも大きな勢力となったのが、1893年にオハイオ州で結成された反酒場連盟(アンチ・サルーン・リーグ、ASL)です。

彼らはジョン・ロックフェラーら財界の支援を受け、1億枚に及ぶビラ、ポスター、パンフレットを配布するなどして大衆へ呼びかけつつ、議会にも盛んに働きかけをしました。
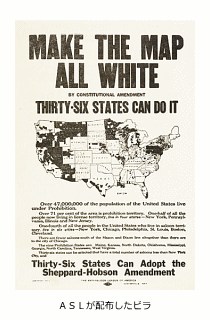
ASLが批判の矛先を向けたのは、酒ではなく団体の名称どおりサルーン、酒場でした。飲酒はキリスト教の教義に背いておらず、禁酒(ドライ)派はアメリカ人の精神の主柱たる個人の自由を侵害しているという、反禁酒(ウェット)派の主張に対して、賭博や売春の温床になっている酒場こそ諸悪の根源だと訴えたのです。
実際、当時の酒場の風紀はひどく乱れていたうえ、たむろしていた新移民は安息日にも騒ぎ、月曜日は二日酔いで仕事を休む、いわゆる「ブルーマンデー」を繰り返しており、悪習に染まる下層階級への嫌悪感が社会に満ちていました。
全米禁酒法と翌年の1921年に施行された移民制限法のジョンソン法は、じつは、ともに新移民に対する排外主義が背景にあったのです。
なお、もうひとつの有力な社会的勢力の労働組合は、禁酒にはおおむね反対の立場をとっていました(酒造業界と小売業はかなりの組合員を抱えており、例えば、クーパーレイジ、樽工場の支部だけで、19世紀の前半には8千人が加入していた)。
さて、行政も規制に乗り出し、酒場の営業許可料を大幅に引き上げました。多くの酒場が経営に行き詰まるなか、自社の商品だけを仕入れることを条件に、ビール会社が補助金を与えるタイドハウス、特約酒場が増えていきます。

その結果、スピリッツ(おもにウイスキー)の一人あたりの年間消費量が、ピークの1830年の7.1ガロンから1900年には1.7ガロンに落ちるいっぽうで、ビールは23.7ガロンへと、同時期に10倍以上に伸びました(ただ、禁酒運動が功を奏し、1850年以降、純アルコールに換算した消費量はあまり変わっていない。下表参照)。

そして、1890年代の「ウイスキー・トラスト事件」で力を削がれたウイスキー業界に代わって、ビール業界が相対的に優位に立つようになります。ドイツ系移民が上質のラガービール(バイエルン地方が発祥)を生産し始めたのも理由でした。

両者は縮小しつつあった市場を巡って反目し、禁酒派に結束して対応できずにいた1913年、ウィリアム・タフト大統領が拒否権を発動したにもかかわらず、一本の重要な法案が上下院の賛成多数で成立しました。「ケニオン・ウェッブ法」です。
従来、州をまたぐ通商に関して州政府に権限はなく、禁酒州は州内での酒類の製造、販売は制限できても、他州からの持ちこみを取り締まれずにいたのですが、それを禁止する初めての連邦法でした。
ただ、意義はありながらも密輸が横行して実効性に乏しかったため、ASLはいよいよ憲法修正を求める活動を始めます。おりしも、彼らを勢いづかせる事態が欧州で生じていました。
そう、1914年に勃発した第1次世界大戦です。

ASLのリーダーのウェイン・B・ウィーラーは、禁酒派の急先鋒の上院議員、モリス・シェパードを後押しして、全米禁酒法の素案となる「ホブソン共同決議」の上程を果たします。法案は下院では採択されたものの、憲法修正に必要な上下院の2/3の賛成までは得られませんでした。しかし、時間は彼らに味方していました。

日増しに悪化していく世論の対独感情(アイルランド系は敵の敵たるドイツを支持した)に乗じ、ASLはビール業界への非難を強めます。ビール会社の経営者の大半がドイツ系(しかもカトリック)だったからです。
「ビール会社はドイツの手先でアメリカの堕落を目論んでいる」、「タイドハウスはスパイの巣窟だ」、「ビールには毒が混ぜられている」といったデマがまことしやかに流され、巧みに愛国心を煽りながら反禁酒派の抵抗を封じていきました。
すでに禁酒法を実施していた州も、すべてが全面的な飲酒を禁じる、ボーン・ドライ、もしくはティートータル、絶対禁酒を布いていたわけではなく、ビールやワインなどアルコール度数の低い醸造酒については比較的寛容でした。あくまで絶対禁酒を目指していたASLにとって、ビール業界を糾弾できる格好の口実を得た第1次世界大戦は、またとない好機となったのです。
#アメリカン・ウイスキーの歴史と製法
